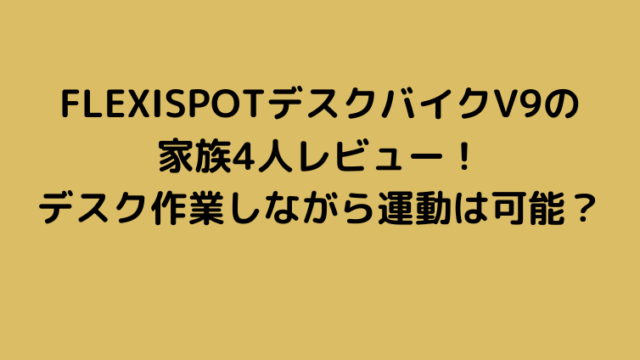プラスチックのボトルは、軽くて持ち運びに便利ですし、毎日の生活に欠かせない存在になっていますね。
仕事に持っていったり、スポーツには必需品です。
お子さんがいるご家庭では、ストロー付きのボトルが便利ですよね。
暑い季節には、麦茶を作ったりする冷水筒が大活躍です。
我が家でも、いろいろなプラスチックのボトルを使っていますが、臭いが気になることがあります。
いつも適当に洗っているので、効果的な洗い方を知りたいと思い調べたら、 臭い取りには、臭いのもとが何かによって、最適な方法が違うことがわかりました。
というように、方法を使い分けるのがおすすめです。
また、プラスチック水筒の気になるくもりやカビを取る方法も調べました!
この記事がお役に立てるとうれしいです。
Contents
プラスチックのボトルの臭いをとる方法は?
ネットで検索すると、臭いをとる方法が山ほど出てきます。
どれを試して良いかわからないくらいです。
臭いには、酸性の臭いとアルカリ性の臭いがあります。
重曹は酸性の臭いに、酢・クエン酸はアルカリ性の臭いに効果があります。
情報を整理して、臭いの原因別に、臭い取りの方法を主婦歴20年の私の経験から勝手に厳選したところ、次のように分類できました。
次から順番に紹介していきます。
【油脂や牛乳などタンパク質汚れが原因の場合】重曹液につける方法
重曹はアルカリ性なので、酸性の臭いを中和します。
油脂や牛乳などのタンパク質汚れに効果があります。
買ったばかりのボトルの油臭さが気になる時にも使えますね。
重曹は100円ショップやドラッグストアで売っています。
↓

水1リットルあたり大さじ2~3杯の重曹をよく溶かします。
これにボトルや各パーツを漬け込み、1~2時間後、よくすすぎます。
40~50℃のお湯を使うとさらに効果が期待できます。
【雑菌が原因の場合】消毒する方法
消毒することにより、プラスチックについてしまった細かい傷の中の雑菌を除菌し、消臭できます。
プラスチックのボトルの消毒の方法には
といった方法があります。
おすすめの順に紹介します。
ハイターなど漂白剤につける方法
漂白剤は、プラスチックについてしまった細かい傷の中の雑菌を除菌し、消臭できます。
ただし、金属部分には使えません。
ふたの部分に金属の部品がついているなどの場合は、そこには薬剤がつかないようにしてくださいね。
【漂白剤の選び方】
お持ちのボトルの素材を確認して、塩素系を使うのか、酸素系を使うのか選んでくださいね。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
・塩素系漂白剤(ハイター)・・・効き目が抜群。人体や環境には優しくない。メラミンには使えません
・酸素系漂白剤・・・効き目は穏やか。人体や環境に優しい。メラミンにも使えます
それぞれの使い方を順に説明します。
塩素系漂白剤(ハイター)の使い方

50ml(キャップ約2杯強)の漂白剤を、5リットルの水に入れます。
よく混ぜてから、ボトルやパーツを2分間漬け込みます。
この時、金属部分は浸からないようにしてください。
その後、よく水ですすいでください。
注意点
・メラミンには使えません。
・塩素系漂白剤と他の製品を混ぜると有害な塩素ガスが出ます。
単独で使用してください。
・換気に注意して、衣服や手につかないよう注意してください。
酸素系漂白剤の使い方

2リットルの水に10g(大さじ1弱)の漂白剤を混ぜ、ボトル・ふた・パッキンなどを30分間漬け込みます。
金属部分は入れないでください。
その後、よくすすいでください。
30~50℃くらいのお湯を使うと、さらに効果的です。
消毒スプレーをする
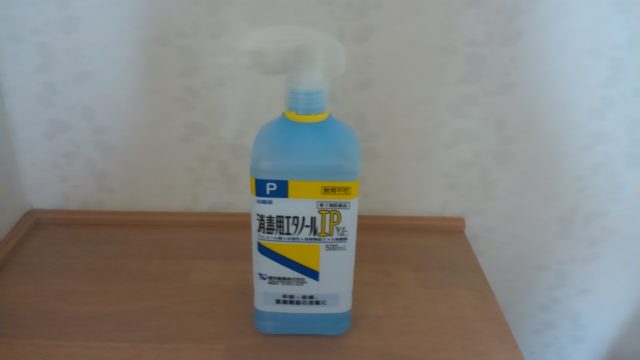
消毒スプレーは、ドラックストアで手に入ります。
ノズル付きなので、シュッと吹きかけるだけで殺菌できます。
無水エタノールというのも一緒に売っていますがが、薄めて使う必要があります。
消毒用エタノールなら、そのまま使えて便利です。
一つ持っていると、ボトル以外でも、気になった時に使えます。
たとえば、家族にインフルエンザの人がいて、ドアノブを消毒したい。などの時です。
ボトルに使って気になる場合は、さっとゆすいでから飲み物を入れてくださいね。
私は、こちらの「パストリーゼ」という消毒スプレーを使っています。
酒屋さんが作っている、食べ物にも吹きかけることのできる消毒スプレーで、とてもおすすめです。
調理器具・掃除・出来上がったお弁当まで、用途は幅広いです。
アルコール度数も70%以上ありますので、感染予防にも使えます。
↓
熱湯消毒する

薬品がない場合は、熱湯消毒ができます。
衛生管理基準としては、75℃1分の加熱条件が示されています。
サルモネラ、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオなどの食中毒菌は、75℃で1分間加熱すると死んでしまうということです。
お手持ちのプラスチックのボトルの耐熱温度を確認して、75℃以上であれば、熱湯消毒が可能です。
方法は簡単で、75℃以上の熱湯に1分間つけるだけです。
薬品を使わないので、一番安全、安心な方法ですね。
鍋でぐつぐつ煮る煮沸消毒は、鍋の底が100℃以上になります。
もし、プラスチックが鍋底に触れると変形の危険があるので、気をつける必要があります。
【水垢が原因の場合】酢やクエン酸の液につける方法
酢やクエン酸は、酸性なのでアルカリ性のニオイを中和します。
水垢はアルカリ性ですので、水垢が臭いの原因の場合は、酢やクエン酸で解決できます。
の順に説明します。
酢を使う方法

お酢は、穀物酢あるいは米酢を使ってください。
ポン酢や寿司酢といった、他の成分が含まれている酢ではできません。
10倍に薄めた酢水に、ボトルや各パーツを1時間ほど漬けたあと、スポンジでやさしく洗ってください。
私もやってみたところ、つけている間や水ですすいだ直後は、酢の臭いが気になりますが、蒸発すると気にならなくなりました。
クエン酸を使う方法

クエン酸は、100円ショップやドラックストアで手に入ります。
1リットルのお湯に25g(大さじ2杯弱)のクエン酸を溶かしてください。
ボトルや各パーツを入れ、1~2時間放置したあと、スポンジでやさしく洗いすすぎます。
ポイント
「重曹とクエン酸や酢を混ぜる」ことについて
今回調べていて、「重曹とクエン酸や酢を混ぜる」という方法もたくさん見つけました。
両方を混ぜてしまって、アルカリ性・酸性の臭い両方を一度で落とせるなら、一石二鳥だよね!と思いました。
しかしよくよく調べると、この2つを混ぜて使うとお互いの汚れや臭いを落とす性質を打ち消しあってしまう、との情報も出てきました。
重曹やクエン酸・酢は、単独で使う方が、効果を発揮するようです。
よって、今回は「重曹とクエン酸や酢を混ぜる」方法はオススメに入れませんでした。
身近にあるものを利用して臭いの元を取り除く方法
重曹やクエン酸など、薬品が家にない場合、家にあるものでも手軽に臭い取りできます。
この方法は、臭いの原因が何かに関わらず、使うことができる方法です。
の順に紹介します。
塩水でシェイクする方法
塩はどこのご家庭にもありますね。
塩大さじ3と少なめの水を入れて、蓋をした後2分間ほどシェイクします。
濃い塩水の浸透圧の力を利用して、細かいデコボコについている臭いの元をとる原理です。
実際にやった方の口コミも効果があるそうです!
米のとぎ汁につける方法
お米のとぎ汁の中には、界面活性剤の役割をするタンパク質が含まれています。
プラスチックボトルをお米のとぎ汁に1時間ほど漬けたあと、普通の洗剤で洗い流すと、においを元から取ってくれます。
家にあるお米が無洗米の場合は、とぎ汁が出ないのでできないですね。
プラスチックのボトルをずっと使っていると、くもりが気になることがあります。
次は、プラスチックのボトルのくもりをとる方法についてです。
プラスチックのボトルのくもりを取る方法
プラスチックのボトルのくもりについても、すぐ上に出てきた重曹や酢・クエン酸の性質を利用して取ることができます。
くもりの原因と対応する方法は次のとおりです。
くもりの原因と対応する方法
・油脂や牛乳などのタンパク質汚れ(酸性)→ 重曹(アルカリ性)
・水垢(アルカリ性) → 酢・クエン酸(酸性)
・茶渋(酸性) → 重曹(アルカリ性)
・細かい傷 → 消すことはできません
以下をクリックするとそれぞれの方法へ戻ります。
残念ながら細かい傷については、取る方法がありません。
重曹と、酢やクエン酸を単独で使う方法は、私の経験上、効果はバッチリあると思います!
これらの方法を試しても、臭いやくすみ(傷が原因のものを除く)が消えない場合は、雑菌が原因の可能性があります。
上の、【雑菌が原因の場合】消毒する方法の部分へ戻ってご覧ください。
↓
【雑菌が原因の場合】消毒する方法に戻る
長い間使っていると、カビが生えてくることもあります。
次は、プラスチックのボトルのカビを取る方法です!
プラスチックのボトルのカビをとる方法
カビは、殺菌の漂白が必要ですので、先程も出てきた漂白剤で落とします。
作用が強い、ハイターなどの塩素系漂白剤を使うのがおすすめです。
詳しいやり方は、上で紹介したこちらをご覧ください。
↓
→ 漂白剤につける方法に戻る
カビてしまうのは、結構ショックです。
カビや汚れを最小限にするには、正しい洗い方をすることが必要です。
次では、プラスチックのボトルの基本の洗い方について紹介します。
プラスチックのボトルの基本の洗い方は?
プラスチックは柔らかい素材ですので、ゴシゴシ洗うと傷がついてしまいます。
その傷に雑菌が繁殖すると、臭いの原因になりますので、ゴシゴシ洗いはおすすめしません。
また、食器洗い機を使ってよいかどうかは、お手持ちのボトルによりますので、説明書を確認してください。
では、基本の洗い方を解説します!
1.ふた・パッキンを本体から外します
ふタやパッキンの細かい部分は汚れやすく、臭いやカビの原因になります。
各部分を分解して、洗いましょう。
パッキンが外れにくい場合は、爪楊枝などで引っ掛ければ外せます。

2.本体を洗います
傷がつきにくいような柔らかいスポンジなどに、食器用洗剤をつけて優しく洗ってください。
柄のついたボトル用スポンジを使うと、底の方まで楽に洗えて便利です。
その後、たっぷりの流水でよくすすぎましょう。
今回は、100円ショップで売っていた、この柄付きスポンジを使いました!
柔らかくて傷がつかないし、汚れもすっきりしましたよ!


柄付きスポンジがない時は、菜箸とスポンジを輪ゴムでくくりつけて、自作することも可能です!
スポンジは、プラスチックに傷をつけない柔らかいものを使ってください!

3.細かいパーツ部分も洗います
分解したふた・パッキン部分も、食器用洗剤をつけてスポンジやブラシで洗います。
スポンジで届かない部分は、ハブラシや綿棒を使ったり工夫して洗います。


また、100円ショップで細かい部分用ブラシが売っていますので、そういった便利グッズを使ってみるのも楽しいですね。
今回は、これを使ってみました!

パッキンが入っていた部分は、ハブラシではなかなか届きません。
この溝用のブラシは、丸く曲がるので、溝にばっちりフィットします!
道具って大事ですね!

ストロー付きのボトルのストロー部分は、こういったブラシが便利です!
これも100円ショップで売っています。

洗い終わったら、こちらも洗剤の成分が残らないよう、しっかりとすすぎましょう。
4.水分を布巾でふきとり、しっかりと乾燥させましょう
水分が残ったままだと、雑菌が繁殖して臭いの原因になります。
洗ったらすぐに、清潔な布巾で水分を取り除きます。
本体は口をさかさにして、しっかりと水を切りましょう。
本体の中も、布巾を菜箸で挟んで拭きます。

お気に入りのボトルは長く使いたいものです。
次は、プラスチックのボトルをきれいに保つにはどうすればいいかについて説明します。
プラスチックのボトルをきれいに保つには?
まず、プラスチックは傷が付きやすいので、硬いスポンジやブラシは使わないでください。
柔らかいスポンジで優しく洗うことが重要です。
そうすることで、傷つくのを防いで、きれいなままでいられることはもちろん、傷にバイキンが入り繁殖することで臭うのを防ぎます。
ボトルの中に入れるものが水の場合は、汚れがそれほど溜まりませんが、お茶やその他の飲み物を入れると、汚れが溜まりやすいです。
ふたの部分の構造が複雑なので、パッキンなどの部品を細かく分解して洗うのが少々大変ですが、都度お手入れすることで、きれいに保つことができます。
プラスチックのボトルの臭い取りする方法は次のとおりです。
お読みいただきありがとうございました。